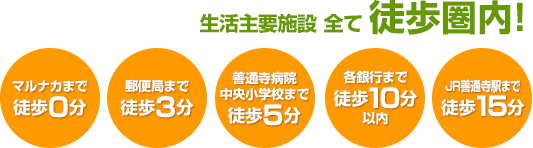カラオケ喫茶アンソロジーノート (28) AKBのつづきのつづき
昭和30年代私が子供の頃。「遍路」はマイナスイメージで捉えられていた。
「お遍路さん」でなく「ヘンド」と呼ばれ差別の目で見られていた。ハンセン病
や犯罪等で故郷を追われ施し(ほどこし)を受け生業(なりわい)として四国遍路を行
なう人達がいたからだ。死に装束を連想させる白衣は汚れに汚れていた (勿論病気
平癒や贖罪による信仰心もあったに違いない、
昭和49年の映画「砂の器」。主人公の新進気鋭のピアニストは大臣の娘と婚約し
輝かしい未来が約束されていた。しかし、幼い頃ハンセン病の父親と物乞いをし
ながら遍路旅をしていた忌まわしい過去を知る恩人が訪ねて来た事から悲劇が始
まる (勿論推理物だから犯人である主人公にたどり着くのは最後だが)。
原作は松本清張の昭和35~6年の新聞小説だ。この頃はハンセン病の治療法は確立
しており、死ぬこともない単なる「感染症」にすぎない。しかし世間はまだ偏見
と差別に満ち溢れていた。清張はそこに目をつけ?題材とした。
映画はそれから10数年後で世間の見方もだいぶ変わったと思うがラストの20
数分?に及ぶピアノ協奏曲に親子の遍路旅がオーバーラップされる。一年中同じ
すげ笠、杖、白衣 (はくえ) の遍路衣装。日本海の吹雪の中をボロボロの衣装で
放浪するシーンは観客の涙を誘う。 (ストーリーの都合上四国ではない )。でも
この涙は可哀そうな身の上だと憐れみの涙でありその奥底にはハンセン病と遍路
に対する偏見と差別がまだまだ見え隠れしていた。
多分平成の今の時代ではハンセン病で遍路旅にピンとこず泣く人もいないだろう
一方これより2年前、四国に住んでる16歳の女の子が自分を見つめ直すため四国遍
路の旅をする高橋洋子主演 「旅の重さ」。吉田拓郎の曲が使われ、青空と入道雲
の下麦わら帽子にジーンズで明るく歩くシーンは今までの遍路のイメージを一変
させた映画だった。今では当たり前のジーンズ姿だ。もっとも当時女の子が一人
で遍路に出るのは物凄く珍しかったと思う。(余談だが高橋洋子が裸でうつ伏せに
座っているポスターが話題になり絶対見なけりゃと思ってたもんだ )
昭和も40年代になると車での「編路」が主流になる。それに伴い本来の信仰心に
基づく参拝が大半となるが、若い人は少なかった。
昭和50年半ばになるとTVで「三都物語」のコマーシャルがキッカケとなって女性
の旅が流行した。そしてただ観光地を訪れるだけでは物足りなさを感じる人が出
てくる。「四国遍路」に目が付けられる。「四国遍路」は「擬死再生」の旅とい
われる。「ぎしさいせい」とは平たく言うと人格再生のために営む儀式でそれは
一度死界に落ちそこから現世に戻って罪深い人から清く美しい人に生まれ変わろ
うというもの。しかしこれではよくわからない。そこである女性誌?が素晴らし
いキャッチコピーを考えた。「自分探しの旅」。こうして失恋したり、仕事や人
間関係に疲れた女性達がゆっくりと時間をかけ自分と向き合う旅に出る。遍路と
いう新しい旅の形であり、これは若い人の男女を問わずブームとなった。
つづく